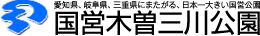旬の花便り
河川環境楽園(木曽川水園・自然発見館)
2021年 旬の花便り一覧
ホトトギス2021年10月15日
こんにちは!木曽川水園ではホトトギスの花が見頃を迎えています。
ホトトギスは花の斑点模様が野鳥のホトトギスの胸の模様に似ている事からこの名が付いたと言われています。とてもユニークな形の花をしており、上向きに咲く花はとても可愛らしいです。
ひっそりとした林床に咲くホトトギスは、涼しげな雰囲気が漂い、秋の訪れを感じさせてくれますね。

直径2~3cmで紫色の斑点のある花。
- ホトトギス【杜鵑草】
- 見頃:10月中旬~11月上旬
ユリ科。
山地のやや湿ったところに生える多年草。茎はふつう分枝せず、高さ0.4~1mになり、崖などに生えたものは垂れ下がる。
遠見の丘や吊り橋付近、茶畑横に等に数十株ずつまとまって植えられています。

茎はまっすぐか斜めに伸び、上向きに花を咲かせる。

白花のホトトギスも見られる。
フジバカマ2021年10月15日
秋の七草では、最後の花「フジバカマ」が見頃です。フジバカマは、華やかさや派手さはありませんが、郷愁を感じる親しみやすい植物です。また、渡りの蝶といわれるアサギマダラが蜜を吸いによってくることでも知られています。
木曽川水園下流部に植栽されていますので、ぜひご覧ください。

たくさんの花が集まって咲きます。
- フジバカマ【藤袴】
- 見頃:10月中旬~下旬
キク科。
川岸の土手などに生える1~2mの多年草。秋の七草のひとつで、乾燥すると香気(クマリン)がある。野生のものは数が減っており、環境省のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種に指定されている。


薄紫色のつぼみに花が咲くと白っぽくなり、糸のようになった雄しべが伸びています。
秋の七草2021年9月15日
少しずつ秋の気配感じることができるようになってきましたが、まだ残暑の厳しい日がありますね。
ところで、「秋の七草」はご存じですか?
「萩の花 尾花葛花 なでしこが花 をみなへし また藤袴 朝顔が花」
(山上憶良 万葉集 巻八 一五三七)
一般的に、ハギ、ススキ、クズ、カワラナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウのことをいいます。
ただし朝顔については、キキョウではなくムクゲやヒルガオという説もあります。
この中から木曽川水園で現在見られる花をご紹介します。どれも下流部で見られますので、探してみて下さいね。

枝垂れた枝葉に花を咲かせ、秋風に揺れる姿は多くの詩歌や文芸に数多く現れていて、古くから日本人に親しまれてきました。
- ハギ【萩】
- 見頃:9月~10月
マメ科。
葉の脇から長い総状花序を出し、紅紫色の蝶型の花がつく。

お月見のお供え物としてかかせないものであり、日本文化の中で秋を象徴する重要な植物です。
- ススキ【薄・芒】
- 見頃:9月~11月
イネ科。多年草
秋の七草で尾花と読まれている。日当たりの良い草地など山野のいたるところに普通に生える。

クズは生育旺盛であっという間に樹木を覆い尽くしてしまい、よいイメージを持たれていない植物でもありますが、花は人知れず葉の下で咲いているものが多く、赤紫色の花は何ともよい香りがします。
- クズ【葛】
- 見頃:9月上旬~中旬
マメ科。
つる状草本で、根は太く大きく多量のでんぷんを含み、葛粉がとれる。和名は大和の国栖(くず)が葛粉の山地であったことから。

オミナエシの鮮やかな黄色の花は遠目にも目を引きます。水辺沿いに植栽されています。
- オミナエシ【女郎花】
- 見頃:7月下旬~10月上旬
オミナエシ科。多年草。
日当たりのよい草原などに生え、高さ1mほどになる。黄色の小さな花を散房状につける。

キキョウの花は、日本では古くから愛される花のひとつで明智光秀の家紋が桔梗紋です。
生憎、花のピークは過ぎてしまい終盤です。
- キキョウ【桔梗】
- 見頃:7月~8月下旬
キキョウ科。多年草。
日当たりのよい山地や野原などに生える。花が美しいために昔からよく栽培されており、八重咲きや白花など園芸種も多い。
ヒガンバナ2021年9月15日
ヒガンバナが見頃です!ヒガンバナは、芽が出て1日に10cm近くも茎が伸び、瞬く間に50cm位になって真っ赤な花を咲かせます。そして、1週間程で花も茎も枯れてしまい球根から緑の葉っぱが出てきます。有毒植物ですが、それを利用しネズミ除けとして畑近くに植えられたり、飢饉のときに球根を食用にしたりと昔から人里では馴染みの深い花であったようです。是非、お出掛けくださいね。

真っ赤な花が鮮やか
- ヒガンバナ【彼岸花】
- 花期:9月~10月
ヒガンバナ科の中国原産の多年草。
秋の彼岸の頃に花が咲くことから由来する。曼珠沙華(マンジュシャゲ)とも呼ばれ、田のあぜや土手、人家の周辺、墓地などに群生することが多い。
水園下流域、中の島、棚田周辺に群生していますので、ご覧ください。


水辺沿いに群生するヒガンバナ 現在つぼみがたくさんあります。

中の島のヒガンバナは遠目でも美しい
かさだ広場のアメリカフヨウ2021年7月16日
国営木曽三川公園かさだ広場で、アメリカフヨウが見頃を迎えております!
アメリカフヨウの花は、ハイビスカスに似ており、夏らしさ満点!花は、ピンク、白、赤など直径20cmを超える大きな花で、かさだ広場の駐車場を囲んで植栽されています。
アメリカフヨウは、日差しの強い日中は元気がなくなってしまいますので、午前中にご覧頂くのがおすすめです。また、かさだ広場駐車場整備のため、アメリカフヨウは、花が終わりましたらすべて抜き取ってしまいます。
ぜひ、今年で最後のかさだ広場の景色を彩る華やかな姿をご覧ください。



ハイビスカスに似た南国風の花。一つの花は1日で終わり午後になるとしおれてしまう。

かさだ広場の駐車場周りに植栽されている
- アメリカフヨウ
- 花期:7月上旬~8月中旬
アオイ科
北アメリカ原産の多年草。
遠くから見ても一目でわかるほど大きな花を多数付ける。
かさだ広場へのアクセスは、木曽三川公園ホームページ「かさだ広場」でご確認ください。
→ かさだ広場へのアクセスはこちら
セイヨウニンジンボクとモクゲンジ2021年7月5日
梅雨末期、じめじめとした蒸し暑い日が続きますね。
中央駐車場北側に目を向けると、薄紫色の花をつけたセイヨウニンジンボクと黄色い花のモクゲンジが目を引きますよ!
ぜひ、ご覧ください。

やや紫がかった青い小花が穂状に咲く。
- セイヨウニンジンボク【西洋人参木】
- シソ科(クマツヅラ科)落葉低木
開花期:6月中旬~9月
ヨーロッパ原産なのでセイヨウ(西洋)、葉がチョウセンニンジンの葉に似ている木なので「セイヨウニンジンボク」と名付けられた。夏から秋にかけて枝の先端に香りがある穂状の薄紫の花を咲かせる。女性のホルモンバランスを改善するハーブとして知られている。

全体に香気があり、薄青紫の花が涼しげ
- モクゲンジ【木槵子】
- ムクロジ科 落葉高木
花期:6月中旬~7月初旬
中国及び朝鮮半島原産。
センダンのような葉を持ち、種子が数珠の材料になることから、別名「センダンバボダイジュ」とも呼ばれる。
花の散る様子を金色の雨に例えて
「Golden rain tree」という英名がある。

開花当初は全体が黄色だが、一両日の内に中央部のふくらみが赤く色づく。

枝先に独特の香りがあるたくさんの黄色い花を咲かせる。
木曽川水園開花情報2021年7月5日
うっとうしい梅雨の季節、園内では、白い豪華な花「ヤマユリ」、鮮やかな橙色の「コオニユリ」、「ヤブカンゾウ」が見頃を迎えております。また、盆花で知られている「ミソハギ」、秋の七草のひとつ「キキョウ」が早くも開花をしています。
是非、お立寄りくださいね!

花は直径15~20cmもある大輪で花びらの内側に黄色い筋と赤い斑点がある。
- ヤマユリ【山百合】
- 見頃:7月上旬~中旬
ユリ科。
山地に生え、高さ1~1.5mの日本原産のユリ。花は大輪で強い芳香があり、白い花の内側には赤い小点がある。リン茎は黄白色の扁球形で、径6~10cmあり食用になる。
木曽川水園上流部吊り橋付近でお待ちしております。

オレンジ色の花を下向きに2~10輪くらいつける。
- コオニユリ【小鬼百合】
- 見頃:7月上旬~中旬
ユリ科。日当たりのよい湿り気のある山地に生える多年草。高さ1~1.5mになりオレンジ色の美しい花が下向きにつく。
オニユリとよく似ているが、オニユリより少し花が小さく、珠芽(むかご:枝の付け根の種のようなもの)を作らない点、茎に顕著な毛がないことで区別できる。
中流トイレから上流トイレに向かう園路沿い、吊り橋付近で見られます。

- ヤブカンゾウ【藪萱草】
- 見頃:6月下旬~7月中旬
ユリ科。多年草。
若葉はおいしい山菜のひとつ。八重咲きになるのが特徴。
水園下流域の周辺で見られます。

- ミソハギ【禊萩】
- 見頃:7月上旬~8月中旬
ミソハギ科。多年草。
高さ1m前後となり、細やかな紫色の花が集まって穂状に咲く。
水園下流域水辺周辺で見られます。

- キキョウ【桔梗】
- 見頃:7月上旬~下旬
キキョウ科。多年草。
秋の七草のひとつ。根は太くて黄白色をしており、多肉室で薬草とされる。
水園下流域の周辺で見られます。
ハンゲショウ2021年6月14日
今年は7月2日が七十二候のひとつ半夏至にあたり、その頃に葉が白くなるハンゲショウが早くも
見頃を迎えています。白と緑のコントラストが涼しげで美しく、水辺の景色を楽しませてくれます。
白くなっている部分は葉で、花は茎の頂部の葉の付け根から白い小さな花を穂状に咲かせます。
開花時に白くなる葉も、夏の盛りには白さが色落ちして緑色っぽい普通の葉になります。
ぜひ、この不思議な仕組みの植物をご覧ください。

上部の葉のみ半分白くなります。
- ハンゲショウ【半夏至】
- 見頃:6月上旬~7月上旬
ドクダミ科。
水辺に白い根茎を伸ばして群生する多年草。和名の半夏至の頃に、花を咲かせることからと言われているが、花が咲くころに上の方の葉が白く変化する「半化粧」とする説もある。
木曽川水園下流部水辺沿いに群生しています。


水辺に群生していて近づくと独特の香りがします。
虎のしっぽ?「オカトラノオ」2021年6月14日
梅雨の時期、涼しげな白い小さい花が可愛らしいオカトラノオが見ごろを迎えています。
「虎の尾」の名の通り、長く細長いしっぽのような形の花序をつけます。枝垂れた花序が風に揺られる様は何とも可愛らしく和みます。ぜひ足をお運びください。

根元から徐々に花を咲かせていきます。
- オカトラノオ【丘虎の尾】
- サクラソウ科 多年草
見頃:6月中旬~下旬
野や山、丘陵地の日当たりの良い草地に生育。花序の形が虎の尾のようである、ということでこの名がついた。花は10㎝~20㎝ほどの大きさで一方に偏り、白い花をたくさんつける。
虎の尾と名のつく植物は多く、オカトラノオによく似た種のヌマトラノオは花序が枝垂れず、直立する特徴がある。
上流トイレ手前の園路沿い、茶畑横に植栽されています。

小さい花が集まり、ふんわりとしたしっぽのようです。
サラサウツギ・ハコネウツギ2021年5月17日
木曽川水園では、花色が白から濃桃へと変化していく様子が魅力的な「ハコネウツギ」、フリルのドレスのような造形とほんのり紅をさしたような色合いがとても可愛らしい「サラサウツギ」が、緑いっぱいの中で色を添えてくれています。
ぜひ、ご覧になってください。

花色の変化が美しいハコネウツギ
- ハコネウツギ【箱根空木】
- 見頃:5月中旬~下旬
スイカズラ科の落葉低木。
沿海地に自生し、観賞用としても広く植えられている。高さは4mほどになる。
葉の脇にラッパ型で先が5つに裂けた花を1輪から3輪ずつつける。
下流域~中流域で見られます。

下向きにまとまって咲く花が可愛いサラサウツギ
- サラサウツギ【更紗空木】
- 見頃:5月中旬~下旬
アジサイ科の落葉低木。
八重咲きで外側が桃色、内側は白色。円錐花序を多数出し、うつむいたようにたくさんの花を咲かす。
下流域・ケヤキ通りで見られます。
木曽川水園開花情報2021年4月8日
今年は、例年より植物の開花が早いです!早くもウラシマソウがあちらこちら顔を出し、見頃を迎えようとしていますよ。木曽川水園 下流部のサトザクラも見頃を迎えていますし、上流部 吊り橋付近ではエビネが開花し始めました。
植物の見頃の時期は、すぐに過ぎてしまいます。是非、お見逃しなく!

黒色の糸を垂らすウラシマソウ
- ウラシマソウ【浦島草】
- 見頃:3月下旬~4月上旬
サトイモ科の多年草。
名前の由来は、花穂の先に伸びている糸状のものを、浦島太郎のつり糸に見立てたところからきている。
糸は長いと30センチ以上になる。
葉が大きいのでわかりにくいかもしれませんが、木曽川水園農家裏の遠路沿いで目線を落としてそのユニークな形をお楽しみください。

葉は空に手を広げるように開き、美しい緑色で光沢がある。

並んで仲良く魚釣り


茎の先に直径4~5cmでふっくらとしたお椀型の白い花をつけるヤマシャクヤク
※2~3日で散る短命花です。お早めにご覧ください。(上流部 垂水の沢)

青紫色の唇型花が一方向につく
ラショウモンカズラ(上流部)

赤紫色の華麗な花シラン
(上流部 農家裏園路沿い)


シックな色合いで気品のあるエビネ。エビネよりひと回り大きい花をつけるキエビネ
(上流部 吊り橋付近)

サトザクラ(下流部)

ベニバナトキワマンサク(下流部)

シロバナトキワマンサク(下流部)
アズマシャクナゲ2021年3月24日
桜の開花と共に山の女王『アズマシャクナゲ』も開花を始めました。
とにかく豪華で美しいです。木曽川水園上流域の「垂水の沢」の中に入ると、深山の雰囲気が感じられ、小鳥のさえずりやせせらぎの音を耳にしながら見事に咲くアズマシャクナゲが目を引きますよ!
ぜひ、ご覧ください。

花が大きく、シャクナゲの中で一番豪華と言われている。
- アズマシャクナゲ【東石楠花】
- ツツジ科 常緑低木
見頃:3月下旬~4月上旬
深山に生える。他のシャクナゲとの見分け方は、アズマシャクナゲの花は5つの切れ込みがあることで見分けが付く。
木曽川水園上流域、垂水の沢でお待ちしております。


つぼみの頃は濃い桃色で咲き進むにつれ薄いピンク色へと変化する。
ヒュウガミズキ2021年3月10日
ヒュウガミズキの開花が始まり、間もなく見頃を迎えますので、ご紹介いたします。木曽川水園中流域のポットリ小屋や茶畑前の川沿いに植栽されていますヒュウガミズキは、淡い黄色の花を下向きに咲かせる控えめな低木ですが、満開時には枝いっぱいに花をつけ、見る人の心を和ませます。
また、枝いっぱいに小さい白い花をつけるユキヤナギも開花を始めています。
是非、「春の訪れ」をお楽しみください。

淡く黄色の花を下向きに咲かせます。
- ヒュウガミズキ【日向水木】
- 見頃:3月中旬~4月上旬
マンサク科の落葉低木。
高さは2~3メートルになる。
1~2cmのやわらかな黄色の花を株一面咲かせ、満開時はとても美しい。
木曽川水園中流域、茶畑前でご覧いただけます。

ポットリ小屋付近のヒュウガミズキ

茶畑前のヒュウガミズキ


ユキヤナギ 遠見の丘にはピンクのユキヤナギが咲いています。
木曽川水園開花情報2021年3月3日
こんにちは!自然発見館です。冷たい風が吹いて肌寒く本格的な春の到来が待ち遠しいですね。
木曽川水園では、春の妖精(スプリング・エフエメラル)として親しまれている“カタクリ”が開花しましたよ!発芽してから開花まで8~9年ほどかかるカタクリの花を見ると、何ともいえない辛抱強さとたくましさ、そして儚い美しさを感じますね。また、これからどんどん暖かくなり、園内の花は一気に開花が進むと思いますので、ぜひご覧ください。

淡い紫色の可愛らしい花を一つ咲かせる。
- カタクリ【片栗】
- ユリ科
見頃:3月下旬~4月上旬
北国に春を告げる花として親しまれている。山野のやや湿ったところに群生する多年草。葉はふつう2枚。花は下向きにつき。開くとすぐに花弁が反り返り、日が当たっているときだけ開く。りん茎から昔は片栗粉をとった。

線香花火のような花が上向きに咲くサンシュユ

黄色い花弁と赤い雌しべのコントラストが美しいトサミズキ


アセビ 白花が基本種。スズランのようで可憐だが葉、花、茎に毒がある。淡紅色の花は写真家に人気。
春の妖精たち2021年2月24日
スプリング・エフェメラル(春の妖精)と呼ばれる植物が開花を始めました!スプリング・エフェメラルとは、春先に花をつけ夏まで葉をつけると、あとは地下で過ごす一連の草花の総称です。林床にひっそりと咲く可憐な花たちをぜひ、ご覧ください。

- ショウジョウバカマ【猩々袴】
- ユリ科
開花期:2月下旬~4月
花色を猩々の顔色に、根生葉の重なりを袴に見立てて名づけられたといわれている。やや湿った所に生える常緑の多年草。高さは10cmから30cmほどになる。花色は淡紅色から濃紫色まで変化が多く、白色のものもある。

- シュンラン【春蘭】
- ラン科
開花期:2月下旬~4月
落葉樹林内などに生える多年草。日本を代表する野生ラン。葉は線形で、ふちに鋸葉がありざらつく。高さ10cmから25cmの花茎の先に淡黄緑色の花を1個開く。

- ミスミソウ【三角草】
- キンポウゲ科
開花期:2月下旬~4月
落葉樹林内などに生える高さ5cmから10cmの多年草。雪の下でも常緑であることからユキワリソウの名でも知られる。葉は常緑で三角形に近く三つに分かれている。花弁のように見えるのは6個から8個の萼片で、色は白、紫、ピンク色などがある。
早春の花2021年2月12日
立春が過ぎ、暦のうえでは“春”「早春の花」と言われる植物が開花を始めています。
まずは、フクジュソウです。フクジュソウの黄色はとても色鮮やか。作り物に思えるほどです。何もない地表に現れたその小さな姿は精一杯の日差しを受けようと懸命に咲いているようにも見えます。

黄色が鮮やか
- フクジュソウ【福寿草】
- キンポウゲ科の多年草
見頃:2月上旬~2月下旬
別名ガンジツソウ(元日草)ともいわれ旧暦のお正月頃に咲くので、おめでたい名がついている。
日が当たる昼間に開花し、夕方には閉じてしまう性質があり、天候の良い日中がシャッターチャンス。
木曽川水園上流の吊り橋付近で見られる。

フクジュカイ
フクジュソウと比べてふっくらとした大輪の花を多数咲かせるフクジュソウの園芸種
遠見の丘で見られる。
フキノトウも見られます。早春に出るフキのつぼみがフキノトウと呼ばれ、春一番の山菜です。

フキノトウ
- フキ【蕗】
- キク科の多年草
見頃:1月下旬~2月下旬
早春、葉に先だって花茎を地上に表し、先端に散房状の花を付ける。雌雄異株。
若い花茎をフキノトウと呼び、早春の味として親しまれる。また、伸びた後の葉柄も食される。
木曽川水園中流域から源流付近まで水辺沿いに多く見られる。
また、セツブンソウが地表からわずか数センチの高さにとても可憐な白い小さな花を咲かせています。

- セツブンソウ【節分草】
- キンポウゲ科の多年草
見頃:2月上旬~下旬
節分の頃に咲くのでこの名がある。とても可愛らしい花をつけ草丈は5cm程と小さく可憐。
花弁に見える白色の部分は蕚で黄色の部分が花弁と呼ばれる部分になる。
木曽川水園中流域で見られる。
いち早く春の訪れを告げるマンサクも黄色い花を咲かせています。

黄色くよじれた紐のような花びらをもち、1箇所に数個まとまって咲く。花弁基部は鮮紅色
- マンサク【満作】
- マンサク科 落葉小高木
花期:2月~3月
日本固有種
リボン状の花びらが特徴。花後は実を付け、熟すと2つに裂けて黒い種子を2つ飛ばす。秋の黄葉も美しい。
ケヤキ通り、水園下流部、農家裏、ふれあい池などで見られる。

中国原産のシナマンサク。花弁基部は暗赤色
※公園スタッフが丹精込めて育てた植物の開花をスタッフはもちろん大勢のお客様が楽しみにしています。どうか園内の植物や生き物等の採取は、絶対にご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
木曽川水園開花情報2021年1月21日
大寒(1月20日)から立春(2月2日)までが一番寒い時期といわれています。
木曽川水園では、ソシンロウバイや梅、フクジュソウが開花を始めています。花の少ない真冬に咲く姿は、このコロナ禍の中で心を和ませてくれ、強さやたくましさを感じさせてくれますね。


黄色い芳香のある花を下向きまたは横向きにつけ、透き通った花びらがまるで蝋細工のように美しい
- ソシンロウバイ【素心蝋梅】
- ロウバイ科の落葉低木
花期:1月~2月
江戸時代に渡来し、観賞用によく植えられる。ロウバイは内側の花弁が茶褐色で、ソシンロウバイは花全体が透き通るような黄色で花径は約2㎝。
農家裏で見られます。


新館裏のソシンロウバイとロウバイは見頃

現在、吊り橋付近のフクジュソウが開花
- フクジュソウ【福寿草】
- キンポウゲ科の多年草
見頃:2月上旬~2月下旬
古くから福を招き、長寿を意味する花として親しまれ、旧正月の頃に咲くことから別名ガンジツソウ(元日草)ともいわれる。
日が当たる昼間に開花し、夕方には閉じてしまう性質があり、天候の良い日中がシャッターチャンス。
遠見の丘、茶畑上部の開花はもう少し先になります。

梅林の白梅

農家裏の紅梅
冬の自然造形美 シモバシラ!!2021年1月12日
こんにちは!三連休は寒い日になりましたね。昨年は、暖冬のため一度も見ることができなかったシモバシラが、今年は氷点下の朝が続いたので、たくさんの枯茎に氷の結晶が見られました。
今シーズンは、氷点下になる朝が幾日か予報されています。もしかしたら、ビューンと長い立派な
氷の結晶が見られるかもしれませんね。
どうぞ、シモバシラが溶けてしまう前に防寒対策をしっかりして、是非お楽しみください。

自然が生み出した芸術!
- シモバシラ【霜柱】
- シソ科 多年草
気温の低い午前中にしか見る事ができません。(※降雪、強風時はでません)
枯れた茎に霜柱のような氷の結晶ができることが名前の由来です。
気温が上がってくると溶けてしまいますので、午前中の中でも早めのご来園をお勧めします。
木曽川水園上流部で見られます。


枯茎に氷の結晶がついています。