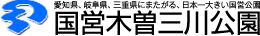旬の花便り
河川環境楽園(木曽川水園・自然発見館)
【園内花情報】ホトトギス2024年10月30日
こんにちは!木曽川水園ではホトトギスの花が見頃を迎えています。
ホトトギスは花の斑点模様が野鳥のホトトギスの胸の模様に似ている事からこの名が付いたと言われています。とてもユニークな形の花をしており、上向きに咲く花はとても可愛らしいです。
ひっそりとした林床に咲くホトトギスは、涼しげな雰囲気が漂い、秋の訪れを感じさせてくれますね。

直径2~3㎝で紫色の斑点のある花。
- ホトトギス
【杜鵑草】 - 花期:10月~11月
ユリ科。
山地のやや湿ったところに生える多年草。茎はふつう分枝せず、高さ0.4~1mになり、崖などに生えたものは垂れ下がる。
遠見の丘や吊り橋付近等に数十株ずつまとまって植えられています。


茎はまっすぐか斜めに伸び、上向きに花を咲かせる。白花のホトトギスは吊り橋付近で見られる。
【園内花情報】フジバカマ2024年10月25日
秋の七草では、最後の花「フジバカマ」が見頃です。フジバカマは、華やかさや派手さはありませんが、郷愁を感じる親しみやすい植物です。また、渡りの蝶といわれるアサギマダラが蜜を吸いによってくることでも知られています。
木曽川水園下流部に植栽されていますので、ぜひご覧ください。

茎の先端に直径5mmほどの小さな花を長さ10cm前後の房状に多数咲かせます。
- フジバカマ
【藤袴】 - 見頃:10月中旬~下旬
キク科。
川岸の土手などに生える1~2mの多年草。秋の七草のひとつで、乾燥すると香気(クマリン)がある。野生のものは数が減っており、環境省のレッドデータブックにおいて絶滅危惧種に指定されている。


薄紫色のつぼみに花が咲くと白っぽくなり、糸のようになった雄しべが伸びています。
アサギマダラが吸蜜する植物としても有名で水園にも訪れました!
【園内花情報】ヒガンバナ2024年10月2日
猛暑日が続きヒガンバナの開花が遅れていましたが、ようやく見頃を迎えていますよ!
ヒガンバナは、芽が出て1日に10㎝近くも茎が伸び、瞬く間に50㎝位になって真っ赤な花を咲かせます。そして、1週間程で花も茎も枯れてしまい球根から緑の葉っぱが出てきます。有毒植物ですが、それを利用しネズミ除けとして畑近くに植えられたり、飢饉のときに球根を食用にしたりと昔から人里では馴染みの深い花であったようです。満開時の川辺を真っ赤に染める風景は圧巻ですよ!
是非、お出掛けくださいね。

真っ赤な花が鮮やか
- ヒガンバナ
【彼岸花】 - 花期:9月~10月
ヒガンバナ科の中国原産の多年草。
秋の彼岸の頃に花が咲くことから由来する。曼珠沙華(マンジュシャゲ)とも呼ばれ、田のあぜや土手、人家の周辺、墓地などに群生することが多い。
水園下流域、中の島、棚田周辺に群生していますので、ご覧ください。

水辺沿いに群生するヒガンバナ

【園内花情報】秋の七草2024年9月18日
9月も中頃となったにもかかわらず、連日猛暑が続きますね!
ところで、「秋の七草」はご存じですか?
「萩の花 尾花葛花 なでしこが花 をみなへし また藤袴 朝顔が花」
(山上憶良 万葉集 巻八 一五三七)
一般的に、ハギ、ススキ、クズ、カワラナデシコ、オミナエシ、フジバカマ、キキョウのことをいいます。
ただし朝顔については、キキョウではなくムクゲやヒルガオという説もあります。
この中から木曽川水園で現在見られる花をご紹介します。どれも下流部で見られますので、探してみて下さいね。

枝垂れた枝葉に花を咲かせ、秋風に揺れる姿は多くの詩歌や文芸に数多く現れていて、古くから日本人に親しまれてきました。
- ハギ
【萩】 - 見頃:9月~10月
マメ科。
葉の脇から長い総状花序を出し、紅紫色の蝶型の花がつく。

お月見のお供え物としてかかせないものであり、日本文化の中で秋を象徴する重要な植物です。
- ススキ
【薄・芒】 - 見頃:9月~11月
イネ科。多年草
秋の七草で尾花と読まれている。日当たりの良い草地など山野のいたるところに普通に生える。

クズは生育旺盛であっという間に樹木を覆い尽くしてしまい、よいイメージを持たれていない植物でもありますが、花は人知れず葉の下で咲いているものが多く、赤紫色の花は何ともよい香りがします。
- クズ
【葛】 - 見頃:9月上旬~中旬
マメ科。
つる状草本で、根は太く大きく多量のでんぷんを含み、葛粉がとれる。和名は大和の国栖(くず)が葛粉の山地であったことから。

オミナエシの鮮やかな黄色の花は遠目にも目を引きます。水辺沿いに植栽されています。
- オミナエシ
【女郎花】 - 見頃:7月下旬~10月上旬
オミナエシ科。多年草。
日当たりのよい草原などに生え、高さ1mほどになる。黄色の小さな花を散房状につける。

キキョウの花は、日本では古くから愛される花のひとつで明智光秀の家紋が桔梗紋です。
生憎、花のピークは過ぎてしまい終盤です。
- キキョウ
【桔梗】 - 見頃:7月~8月下旬
キキョウ科。多年草。
日当たりのよい山地や野原などに生える。花が美しいために昔からよく栽培されており、八重咲きや白花など園芸種も多い。
【園内花情報】木曽川水園下流部開花情報2024年7月23日
毎日猛暑が続いており、じゃぶじゃぶの河原は水遊びを楽しむ子供たちで大変賑わっています。
さて、木曽川水園下流部では「盆花」とも呼ばれるミソハギや秋の七草であるオミナエシやキキョウ、カワラナデシコが開花を始めております。また、ナツズイセンも可愛らしいピンク色の花を咲かせていますよ。是非、熱中症予防をしっかりしてお立寄り下さいね!

一つの花は1㎝弱で穂状につき、水辺の周りにまとまって植栽されている。
- ミソハギ
【禊萩】 - 花期:7月~9月
ミソハギ科。
山野の湿地に生える多年草。和名は溝萩(みぞはぎ)または禊萩(みそぎはぎ)からきたとの説がある。高さ1m前後となり、細かな紫色の花が集まって穂状に咲く。

小さな黄色い花が集まって咲く。
- オミナエシ
【女郎花】 - 花期:7月~9月下旬
オミナエシ科。多年草。
日当たりのよい草原などに生える。
高さ1m内外になる。同属に白い花を付けるオトコエシもある。

涼しげな青紫色の星形の花と紙風船のようなつぼみ
- キキョウ
【桔梗】 - 花期:6月~9月
キキョウ科。多年草。
日当たりのよい山野に見られる。
草丈50㎝~100㎝程になり、紙風船のような蕾から星形の美しい花を咲かせる。野生種のものは減少傾向にあり絶滅危惧種に指定されている。

淡いピンク色の花が可愛い
- ナツズイセン
【夏水仙】 - 花期:7月下旬~8月中旬
ヒガンバナ科。
人里近くの山野に野生化する多年草。
和名は葉がスイセンに似ていて、花が夏に咲くことから。夏前に葉が枯れた後、50~70㎝の花茎を出し数輪のピンク色の花を付ける。

花弁に細かい切れ込みは入っていることが特徴
- カワラナデシコ
【河原撫子】 - 花期:7月~9月
ナデシコ科。多年草。
日当たりのよい草原や川原などに生える。
淡い紅色や白い可憐な花を咲かせる。花弁は5枚で先端が細かく裂けている。
【園内花情報】ヤマユリ2024年7月1日
蒸し暑い日が続きますね。本日は、白い大きな花を咲かせているヤマユリが咲き始めましたので、ご紹介します。近くに行くと、まず先に香りに気づくでしょう。とても芳香の強いユリで、花は大きく豪華で、見事ですよ。ぜひ、ご覧ください。

茎先に香りのよい漏斗状の花をつける。
- ヤマユリ
【山百合】 - 見頃:7月上旬~中旬
ユリ科。
山地に生え、高さ1~1.5mの日本原産のユリ。花は大輪で強い芳香があり、白い花の内側には赤い小点がある。リン茎は黄白色の扁球形で、径6~10㎝あり食用になる。
木曽川水園上流部吊り橋付近でお待ちしております。

花は直径20㎝くらいある大輪で花びらの内側に黄色い筋と赤い斑点がある。

つぼみが多数あり、数日中には開花し見頃を迎える。
【園内花情報】ハンゲショウ2024年6月10日
今年は7月1日が七十二候のひとつ半夏至にあたり、その頃に葉が白くなるハンゲショウがまもなく見頃を迎えます。白と緑のコントラストが涼しげで美しく、水辺の景色を楽しませてくれます。
白くなっている部分は葉で、花は茎の頂部の葉の付け根から白い小さな花を穂状に咲かせます。
開花時に白くなる葉も、夏の盛りには白さが色落ちして緑色っぽい普通の葉になります。
ぜひ、この不思議な仕組みの植物をご覧ください。

上部の葉のみ半分白くなります。

水辺に群生していて近づくと独特の香りがします。
- ハンゲショウ
【半夏至】 - 見頃:6月上旬~7月上旬
ドクダミ科。
水辺に白い根茎を伸ばして群生する多年草。和名の半夏至の頃に、花を咲かせることからと言われているが、花が咲くころに上の方の葉が白く変化する「半化粧」とする説もある。
木曽川水園下流部水辺沿いに群生しています。
【園内花情報】木曽川水園開花情報2024年4月24日
春本番となり、木曽川水園では植物の開花がどんどん進んでいますので、ご紹介します。
株一面にかわいらしい白い花をたくさん咲かせるヒメウツギ。ヒメウツギの株はコンパクトにまとまり、庭木としても人気があります。「ウツギ」と名前がつく樹木はいくつもありますが、実は異なった種であり、茎の中が空洞である事から「空木」と呼ばれているようです。また、ミツバウツギも清楚な白い花を咲かせていますよ。

伸びた茎の先にベル型の白い花を下向きにつける

岩場の間から白い花が顔を出し、山の雰囲気を醸し出す
- ヒメウツギ
【姫空木】 - 見頃:4月下旬~5月上旬
ユキノシタ科の落葉低木。
山地の岩上などに生え、高さ1~1.5mになる。花の大きさは1~1.5㎝。ウツギより小型なのでヒメウツギと呼ばれる。株がコンパクトであり、庭木にもよく利用される。
木曽川水園上流部吊り橋付近、中流部ふれあい池で見られます。

花びらは大きく開かない。葉は3つ集まってつく
- ミツバウツギ
【三葉空木】 - 見頃:4月下旬~5月上旬
ミツバウツギ科の落葉低木
山地に生え、高さ3~5mになる。ウツギの仲間ではないが、葉が三出複葉で茎がウツギと同様に中空であることから名づけられた。花径は1㎝足らずで、閉鎖花も多い。
エビネの花が咲き始めました。エビネは日本原産の野生ランで、花の色や形にそれぞれ違いがあることが面白く、愛好家の方々にも人気の植物です。まっすぐ伸びる花茎に小さな花をたくさんつけ、繊細な印象を与えてくれます。また、近くにはキエビネも植えられています。とてもよく似ていますが、こちらは黄色の花がぱっと目をひき、エビネよりも大型でダイナミックな印象です。是非上流域まで足をのばしてみてくださいね!


シックな色合いで気品のある姿で、花の色が株により違う
- エビネ Calanthe discolor
【海老根】 - 見頃:4月中旬~5月上旬
ラン科の多年草。
山地や丘陵の林下に生える。
地表近くにある根茎が連なっている海老のように見えることから名づけられた。日本に自生するランの仲間で古くから観賞用の植物として親しまれてきた。
木曽川水園上流域つり橋付近で見られます。

キエビネはエビネよりにひと回り大きく、黄色の花をつける
【園内花情報】木曽川水園開花情報2024年4月11日
今年は、早くもウラシマソウがあちらこちら顔を出し、見頃を迎えています。また、木曽川水園 上流部ではヤマシャクヤク、下流部ではサトザクラが咲き始めました。
植物の見頃の時期は、すぐに過ぎてしまいます。是非、お見逃しなく!


黒色の糸を垂らすウラシマソウ 葉は空に手を広げるように開き、美しい緑色で光沢がある。
※葉が大きいのでわかりにくいかもしれませんが、農家裏の遠路沿いで目線を落としてそのユニークな形をお楽しみください。

茎の先に直径4~5㎝でふっくらとしたお椀型の白い花をつけるヤマシャクヤク
※2~3日で散る短命花です。お早めにご覧ください。(上流部 垂水の沢)

枝先に3枚のひし形の葉をつけ鮮やかな紅紫色の花をつけるミツバツツジ

葉や茎がネバネバし、触ると指が貼りつくことからモチツツジと名付けられた。
枝先に2~3輪ずつ紅紫の花をつけます。

八重の大きな花が特徴のサトザクラ(下流部 遠見の丘)

ベニバナトキワマンサクとナノハナのコントラストが美しい。(下流部)
【園内花情報】「アズマシャクナゲ」の開花!2024年4月1日
桜の開花と共に山の女王『アズマシャクナゲ』も開花を始めました。
とにかく豪華で美しいです。
木曽川水園上流域の「垂水の沢」の中に入ると、深山の雰囲気が感じられ、小鳥のさえずりやせせらぎの音を耳にしながら見事に咲くアズマシャクナゲが目を引きますよ!
ぜひ、ご覧ください。

花が大きく、シャクナゲの中で一番豪華と言われている。
- アズマシャクナゲ
【東石楠花】
ツツジ科 常緑低木 - 見頃:3月下旬~4月上旬
深山に生える。他のシャクナゲとの見分け方は、アズマシャクナゲの花は5つの切れ込みがあることで見分けが付く。
木曽川水園上流域、垂水の沢でお待ちしております。


つぼみの頃は濃い桃色で咲き進むにつれ薄いピンク色へと変化する。
【園内花情報】木曽川水園開花情報2024年2月26日
今年は寒暖差が激しく、植物もびっくりしていると思います。
木曽川水園では 「早春の花」と言われる植物が次々と開花を始めていますので、ご紹介します。
まずは、フクジュソウです。何もない地表に現れたその小さな姿は精一杯の日差しを受けようと懸命に咲いているようにも見えます。

フクジュソウ
黄色が鮮やか。陽があたる昼間に開花し、夕方には閉じてしまう。吊り橋付近で見られる。


フクジュカイ
フクジュソウと比べてふっくらとした大輪の花を多数咲かせるフクジュソウの園芸種
遠見の丘で見られる。現在、終盤
また、セツブンソウが地表からわずか数センチの高さにとても可憐な白い小さな花を咲かせています。

セツブンソウ
中心の雄しべが青みがかり、小さな白い花は妖精にも例えられる。
辻の茶屋裏側及び吊り橋付近で見られる。
雪割草とも呼ばれるミスミソウも可愛い花を咲かせています。


ミスミソウ
ほかの花に先駆けて色とりどりの花を咲かせるので多くの人に親しまれている。
吊り橋付近で見られる。
いち早く春の訪れを告げるマンサクが黄色い花を咲かせています。

マンサク
黄色くよじれた紐のような花びらをもち、1箇所に数個まとまって咲く。花弁基部は鮮紅色
木曽川水園下流部、ケヤキ通り、農家裏で見られる。現在、咲き始め

シナマンサク
中国原産。花弁基部は暗赤色。ふれあい池で見られる。現在、満開
しずく形の花を房状にたくさんつけるアセビも咲き始めました。


アセビ
満開になると株一面を覆うように花をつける。
自然発見館前、木曽川水園中流・上流部で見られる。現在、咲き始め
【園内花情報】セツブンソウ開花!2024年2月13日
立春が過ぎ、暦の上では“春”です。ここ数日の暖かさでセツブンソウが開花を始めました。セツブンソウは地表からわずか数センチの高さに白い花をつけ、とても可憐ではかなげです。現在、つぼみが多数ありますので順次開花が進むと思います。ぜひ、ご覧ください。

中心部の雄しべが青みがかり、小さな白い花は妖精にも例えられます。
- セツブンソウ
【節分草】 - キンポウゲ科の多年草
見頃:2月中旬~3月上旬
節分の頃に咲くのでこの名がある。とても可愛らしい花をつけ草丈は5cm程と小さく可憐。
花弁に見える白色の部分は蕚で黄色の部分が花弁と呼ばれる部分になる。

現在、つぼみが多数あります。